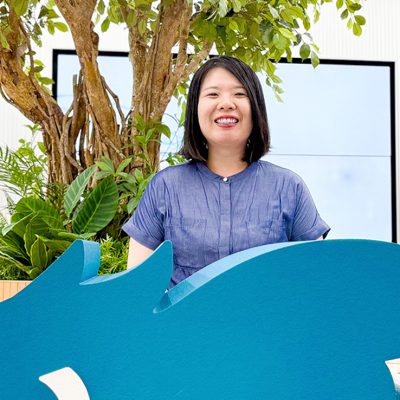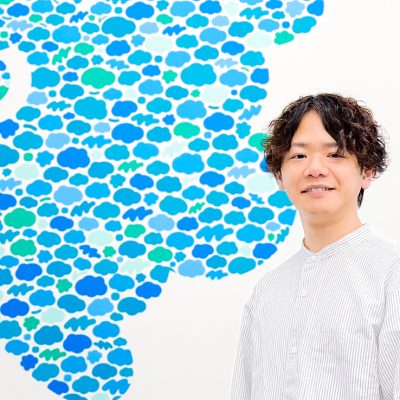Voice
社員インタビュー

執行役員
企画本部 本部長
兼 CPO
白石 久也
大学卒業後、独立系SIerに入社しエンジニアとして金融系システムの開発に携わったのち、2002年ヤフー株式会社に入社。プロダクトマネージャーや事業責任者としてYahoo!メールやYahoo!プレミアムなど20以上のサービスを担当。2018年に株式会社GYAOの取締役となり、プロダクト責任者として開発部門を管掌。2021年、Z Entertainment株式会社 CPO室長となり、エンタメ領域プロダクトの戦略立案をリード。
2022年6月にセーフィー株式会社(以下セーフィー)に入社。2023年1月から執行役員・CPOとして、新規・既存プロダクトの企画・開発やプロダクトを絡めたビジネス開発全般を統括。(所属部門・役職はインタビュー時のものです)
セーフィーの企画本部で本部長 兼 CPOを務めている白石さんは、約20年間にわたってヤフー株式会社で活躍し、様々なサービスの立ち上げや運営、立て直しなどをリードしてきたキャリアの持ち主です。今回のインタビューでは、そんな白石さんがセーフィーに入社した経緯や理由についてお聞きするとともに、企画本部のPdMとしてセーフィーのプロダクト開発に携わる魅力やメリット、セーフィーのPdMと他社のPdMとの業務範囲の違い、セーフィーのPdMに求められるスキル・マインドなどについて、詳しくお話しいただきました。
今まで以上にチャレンジングな環境で働きたいと考え、転職を決意
最初に白石さんのセーフィー入社以前のキャリアを教えてください。
大学卒業後、社員数1000名規模のSIerに入り、金融系システムを開発するエンジニアとして働いていました。その会社には5年ほど在籍しましたが、より多くのユーザーに直接価値を届けられる仕事に挑戦したいと考えるようになり、知人の紹介を受けてヤフーに転職しました。
私が転職した2002年当時のヤフーは、米国Yahoo! Inc.のサービスを日本向けにローカライズするビジネスを推進していたため、社員数400名規模の会社であったにも関わらず、100以上のサービスを運営していました。そのため、エンジニアの経験しかなかった私も企画職というポジションで入り、入社早々にYahoo!メールを担当することになりました。
それから数年も経たないうちにYahoo!メールのサービス責任者となり、Yahoo!メール、Yahoo!プレミアムのほか、十数年の間に20以上のサービスに携わりました。新規サービスの立ち上げはもちろん、右肩下がりだったサービスの立て直しやサービスのクローズなど、サービスを「作る・育てる」ことに関する幅広い経験を積むことができたほか、会社が大きくなっていく過程でメンバー、リーダー、部長、本部長、子会社役員などを任せてもらい、組織づくりやマネジメントに関する経験も積ませていただきました。
何故、ヤフーからの転職を考えられたのですか?
ヤフーで約20年働き続けていたので、役職者のほとんどが知り合いで人脈も出来上がっており、多少難度の高い案件を頼まれたとしても、それまでの経験である程度の進め方が分かってしまうような状況でした。端的に言えば、仕事が楽になってしまったことに物足りなさを感じるようになったのです。いろいろと選択肢はあったと思いますが、これまでの経験を活かしつつ、今まで以上にチャレンジングな環境で働いてみたいと思い、転職を考えるようになりました。
転職先を探す際に重視していたポイントはありましたか?
1つ目は事業領域です。ヤフーでは長年toCのサービスに携わってきましたが、新たな挑戦として今度はtoBのサービスで自身の経験を活かしたいと考えていました。2つ目は会社のフェーズ。プロダクトに対して大きな影響力を持って関われる規模感で、かつ、スタートアップから成長企業へと転換しようとしている、そんな変革期の企業を探していました。3つ目は業界で、特にヘルスケアやヘルステック分野に大きな可能性を感じていたので、その分野の企業を中心に転職活動を進めていました。

チャレンジの方法自体を設計できる環境に魅力を感じてセーフィーへ
最初にセーフィーを知ったきっかけを教えてください。
転職エージェントの方からの紹介です。当時はtoC以外の業界のことは何も知らなかったので、セーフィーの社名すら知りませんでした。また、自分としてはヘルスケアやヘルステックの企業を希望していたので、最初は興味の範疇外でしたが、転職エージェントの方に熱意を持って勧めていただいたこともあり、取り敢えず面接を受けてみようと思ったのです。
どのようなことがセーフィーへの入社の決め手になったのですか?
一次面接で映像プラットフォームに関する説明を聞いた段階では、私のtoC事業での経験が活かせるのか、という懸念がありました。ただ、二次面接で代表の佐渡島から「すでにクラウドカメラで確固たる市場ポジションを確立しており、これから各業界向けに様々なソリューションを展開していくフェーズに入る」「toCサービスで培った経験やノウハウを活かすことで、toB領域でも圧倒的な競争優位性を築ける」というビジョンに、大きな共感を覚えました。セーフィーが今まさに変革期を迎えており、新しいチャレンジの設計から携われるタイミングであることが理解でき、企画職としては「これ以上ないタイミングでこの会社に巡り会えたのかもしれない」と感じたことが入社の決め手になりました。
CPOとしてプロダクト企画を行う前に、組織課題解決から取り組まれたと聞きました。
入社当初はグループ子会社の立ち上げに携わる予定でした。ただ、入社後に複数の役職者から組織課題に関する意見を聞くことがあり、せっかくなら組織課題の解決に取り組んでみようと考えました。
社内の一定以上のレイヤーの役職者全員にヒアリングを行い課題を抽出してみると、セーフィーの組織が急激に大きくなり、組織構造が複雑化したことから課題が生じていることが見えてきました。
私は経営陣に組織構造の改善を提案し、その改善案をベースにした新組織が始動することになりました。このような組織課題解決に関する一連の取り組みを終えた後、「せっかく立て直した組織を引っ張って、次はセーフィー本体でプロダクトを創る責任者になって欲しい」と佐渡島から要請があり、CPOに任命されて現在に至ります。
ハード・SaaS・AIなど、様々な要素が絡む複雑性の高いプロダクト開発
企画本部 本部長 兼 CPOとして、白石さんが統括されている企画本部のミッションや組織体制を教えてください。
企画本部は、社内外のステークホルダーをリードしながらセーフィーのプロダクト開発とビジネス構築を実現するというミッションを担っている部門です。社員数50名程度の組織であり、PdM(プロダクトマネージャー)、デザイナーが半々くらいの割合で所属しています。また、新規事業の創出を担当するビジネス開発(BizDev)チームのメンバーも所属しています。
PdMが担うプロダクト開発の流れについて教えてください。
プロダクト開発の基本的な流れは、一般的なプロセスと大きく変わりません。まず最初に、営業チームやお客様から寄せられる声をベースに市場調査を実施し、ビジネスとしての実現可能性を検証した上で、具体的なアイデアへと落とし込んでいきます。次に、そのアイデアを実現するために必要なリソースを見積もり、社内の承認・決裁を得るための事業計画を立案します。承認が得られた後は、より具体的なビジネスプランの策定とプロダクトの仕様確定に入ります。この際、プロダクト開発と並行してオペレーションの設計も進めていきます。そして、完成したプロダクトをリリースした後は、マーケティング施策や様々なプロモーションを展開し、市場への浸透を図っていきます。このように、アイデアの着想から市場展開まで、一気通貫で推進していく体制を整えています。
セーフィーのプロダクト開発の特徴は、ハードウェア、クラウド・SaaS、AIといった多様な技術要素を統合的に扱う点にあります。たとえばAIソリューションの開発では、AIのアプリケーションだけでなく、AIを搭載するカメラを同時に開発することもあり得ますし、AIが解析したデータを可視化するためのWebビューアーを作る可能性もあります。また、ハードウェアビジネスならではの課題もあります。製品の配送や設置、保守メンテナンスなど、オペレーション面での綿密な設計が求められます。大手企業であれば、これらのバックオフィス業務の仕組みが既に確立されているでしょう。しかし、設立10年目を迎えたセーフィーは、まさにこれらの業務のDX化に取り組んでいる最中です。
オペレーション周りの設計もPdMが担当するのですね。
セーフィーのPdMは、営業部門やカスタマーサービス部門と協働しながら、オペレーションの設計にも深く関わっていきます。またセーフィーの場合、自社の営業チームだけでなく、多くのパートナー企業を通じた販売展開も行っているため、プロダクト開発においては幅広い視点が求められます。
具体的には、パートナー企業の商流に合わせた製品設計や、スムーズな連携を実現するための事前コミュニケーション、さらにはパートナー企業向けのオペレーション設計なども重要な業務となります。パートナー企業との協力体制による強力な販売力は、セーフィーの大きな強みの一つです。そのため、このパートナーシップを最大限に活かせるよう、PdMには細やかな配慮と工夫が求められます。
これまでに白石さんが関わったプロジェクトや業務の中で、とくに印象に残っているものを教えてください。
普段はマネジメントがメインの業務となっているため個別案件に関わることは少ないのですが、主にセキュリティ対策を目的とした小売業界向けの映像×AIプロダクトの開発プロジェクトは特に印象に残っています。このプロジェクトは特定のお客様に向けて開発を進めていましたが、そのお客様は大手企業との取引が中心だったため、当初はベンチャー企業であるセーフィーに対して慎重な姿勢を示されており、なかなか本質的なコミュニケーションを図ることができませんでした。
そこで、私自身もお客様先に足を運び、セーフィーの企業としての理念やプロダクトの強みについて、熱意を持って説明させていただきました。このような地道な信頼関係構築の努力が実を結び、大手企業も参画する最終選考の機会をいただくことができました。
そして実際のコンペでは、品質、価格、導入のしやすさなど、あらゆる観点で当社の映像×AIプロダクトをご評価いただき、最終的に採用が決定。現在では、このお客様とは重要なパートナーとして深い信頼関係を築くことができ、様々な面でご支援をいただいています。

プラットフォームをベースにして、どんなプロダクトでも立ち上げられる環境
セーフィーでPdMの仕事をする魅力・メリットはどこにあると考えていますか?
セーフィーは「映像から未来をつくる」というビジョンを掲げて事業を推進していますが、その未来の創り方には無限の可能性が広がっています。私たちが持つ映像プラットフォームを基盤として、様々な産業や領域に向けた新しいビジネスやプロダクトを創出できる環境があり、PdMにとって、まさに理想的なフィールドが用意されています。
また、セーフィーの特徴的な強みは、ハードウェア、ソフトウェア、AI、設置工事まで、プロダクトに関わるあらゆる要素を自社で一気通貫に手掛けられる点です。この体制により、柔軟かつスピーディーな開発が可能となっています。さらに、状況に応じて他社との協業も選択できるため、プロジェクトの特性に合わせた最適な開発アプローチを取ることが可能です。このように、強力な開発基盤を持ちながら高い自由度で企画立案できることも、セーフィーで働く大きな魅力の一つであると考えています。
さらにセーフィーの特徴的な点として、プロダクト開発とビジネスモデルの構築を同時に推進できる環境が整っていることが挙げられます。
たとえば、新しいプロダクトを企画する際、『レンタル方式か、月額課金か、従量課金か』『完全なSaaSとして提供するか』『自社営業での展開か、パートナー企業との協業か』など、ビジネスモデルの選択肢を幅広く検討しながら開発を進めることができます。
このように、PdMがプロダクトの企画開発だけでなく、ビジネスモデルの設計にまで深く関われる環境は、他社ではなかなか経験できない大きなやりがいにつながっていると考えています。
セーフィーのPdMとして活躍するには、どのようなスキル・マインドが必要になるでしょうか?
求めるマインドとして最も重要なのは、映像技術で社会課題を解決するというセーフィーのミッションに共感し、その可能性に心から『おもしろい!』と感じられることです。その上で必要となる要素が3つあります。
1つ目は、開発チームはもちろん、営業、カスタマーサポート、パートナー企業など、多様なステークホルダーと協働しながらプロジェクトを推進できるコミュニケーション力です。
2つ目は、困難な状況でも『必ずやり遂げる』という強い意志と推進力。
そして3つ目は、様々な業界や業種について、お客様の業務内容や課題に至るまで、深く理解しようとする強い知的好奇心です。
これらの要素を兼ね備えた方であれば、セーフィーのPdMとして大きな活躍が期待できると考えています。
今後、白石さんがセーフィーで成し遂げたいと考えていることを教えてください。
まず目指したいのは、セーフィーの映像プラットフォームを基盤として、社会に価値あるプロダクトやビジネスを次々と生み出していくことです。それぞれのソリューションを大きく育てていけば、独立した事業会社として展開できるほどの規模に成長させることも可能だと考えています。
そして最終的には、映像技術を軸に様々な社会課題を解決する企業グループへとセーフィーを発展させていきたい。これが私の描く将来像です。
最後になりますが、セーフィーのPdMにチャレンジしたいと考えている方々へのメッセージをお願いします。
私自身、ヤフーで企画職としてのキャリアをスタートした際は未経験でしたが、多くのサービスに関する意思決定を任せていただきました。時には判断を誤ることもありましたが、『自分で考えて決める』という経験の積み重ねが、現在の自分を形作る重要な糧となったと実感しています。
セーフィーでも同じように、新しく入社される方々には『自分で考え、決断する機会』を積極的に提供していきたいと考えています。自らの判断で仕事を推進したい方、主体的な挑戦を通じて成長したい方には、きっと魅力的な環境になるはずです。そんな意欲ある方々と一緒に働けることを、心待ちにしています。

Voice